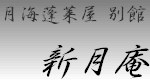
menu
バイトを終え、帰途につく頃には周囲はすっかり蒼い闇に包まれている。
その闇は昼間の熱気を残した大気と共に、包みこむように圧し掛かるように──酷く重苦しく、そこに立ち込めていた。
それはそれで珍しい事でもない──と、思う。少なくとも、季節的にはよくある、寝苦しい夜でしかない。
自転車のライトだけがぼんやりと照らす夜道を走りつつ、セイはそんな事を考えていた。
「連続熱帯夜とか、寝られなくて死ねるんだけどなぁ……」
ぼやくような呟きをもらしつつ、ハンドルを切って角を曲がる。妙に重苦しい大気は疾走時特有の心地良さを感じさせず、むしろ、絡みつくようなその感触が不安めいたものを募らせた。
「……」
横断歩道の前で自転車を止め、信号機のボタンを押す。理由はわからないが、妙に気が急いていた。早く帰りたい、早く帰って皆の──『家族』の声を聞きたい。大気の感触が募らせる苛立ちはいつか、そんな思いをセイに抱かせていた。
「……だってのに……」
苛立ちをこめた呟きが口をつく。
早く帰りたい──というセイの思いとは裏腹に、信号は中々変わらなかった。元々、押しボタンなのに中々変わらない事で有名なポイントではあるが、今日は特にその時間が長く感じられた。
「疲れてんのかなぁ」
また、独り言がこぼれる。不安や苛立ちといった感情が渦を巻き、いっそタイミングを見切って強行突破してやろうか、と危険な考えが過ぎった矢先、前方に青緑の光が灯った。熱気を巻き上げる大型車の流れが止まり、セイは一つ息を吐いてから横断歩道を渡る。
「さってと……」
道を渡った所で、再び思案する。明るくて人通りもある商店街を抜けて行くか、街頭まばらで人通りも少ない川沿いの道を通って真っ直ぐ家へと向かうか。
時間的には、人を避ける必要がほとんどなく、ほぼノンストップでいける後者の方が僅かに早い。時間にすれば五分ほどだが、そのわずかな差が、セイに後者を選ばせていた。
賑やかな町明かりに背を向け、ライトを頼りに蒼い闇の包む領域へと自転車を走らせる。闇に向かうにつれて車の行き交う音は遠ざかり、それと入れ替わるように水の流れる音がやけに大きく聞こえてきた。
「ん、少し涼しい……」
川沿いの道は、吹き抜ける風もわずかに涼を帯び、火照った身体に心地良い。その感触にほっと息を吐きつつ、セイはややスピードを落として自転車を走らせ──。
ぴちゃり。ぴちゃ。ぴちゃ……。
不意に耳に届いた音に、反射的にブレーキをかけた。否──かけてしまった、と言うべきか。
「え……な、な、に?」
川の流れる音とは明らかに異なる、水音。その合間に、笑い声のようなものも微かに聞き取れた。
「……」
気にする事など、ないのかも知れない。この時期、この川原で酒を飲んで騒ぐ連中が出てくるのは取り立てて珍しい事でもないのだから。
そう、割り切ろうとするも何故か、響く音と微かな笑い声が気になって仕方なかった。
「気のせい……考え過ぎだっての……」
自分自身に言い聞かせるように、小さく呟く。だが、その声は微かに震えていた。その震えを振り払うように、首を左右に強く振る。震えと共にふと浮かんだもの──今朝の目覚めの夢をも振り落としたいと、そう思ったのだが。
「あ……あれ、は?」
首を振った事で川原の方へと向いた視線が、それを捉えた──捉えてしまった。川原に座り込む人影らしきもの。暗い事と、陰になっていてよくはわからないが、その前にも倒れているらしい人影がちらりと見て取れた。
「……」
近づいてはいけない。関わってはいけない。
そんな、警鐘めいたものがどこからか響いてくる。
だが、その警鐘も不安も自分の思い過ごしだとしたら、という思いもまた、存在していた。それらは自分の思い込みによるもので、川原では何か現実的なトラブルが起きているのかもしれない。それなら、手を貸した方がいいのかも知れない。微かに感じる異臭も、少し気にかかる。
そんな思いからセイは自転車を降り、川原へと下って行った。川原の人影は、セイに気づいていないらしい。はっきりとはわからないが、倒れている方の人影に対して何かしているらしい──と、そこまで認識した時。踏み出した足が、何かを引っ掛けた。
「ん?」
川原の石とは明らかに違う感触に、セイは何気なく視線をそちらに向ける。それとほぼ同時に吹き抜けた風が月にかかっていた雲を散らし、僅かな光で川原を照らした。
「……っ!?」
僅かな光。それが浮かび上がらせたのは──人の、腕。いや、腕だったモノ、と言うべきだろう。紅黒い中に所々白が覗いているのは、どうやら骨が見えているらしい。つい先ほどまで、何かに喰い荒らされていたかのようなそれは、ごく無造作に、そこに転がっていた。
「……う……あ……」
浮かび上がり、重なる、夢。
闇の中に舞う真紅。ツクリモノのように飛ぶ、引き千切られた四肢。
夢の中で飛んだそれと、目の前のそれは、妙に良く似ていて。
それがより一層強く、二つの光景を結びつけた。
「……」
震えが走る。声が出ない。いや、声を上げてはいけないような、そんな気がする。声を上げたら、気づかれたら、戻れない。そんな気もした。
「……」
口元を片手で覆うようにして、じり、と後ずさる。関わってはいけない、これ以上、踏み込んではいけない。どこからか響く、警鐘。関わったら、踏み込んだら、もう戻れない。
だから、何も見ていない。何も感じてはいない。喰い荒らされた腕も、圧し掛かるような血の匂いも、微かに聞こえる咀嚼音らしきものも。
何も、何も。見ていない、感じていない、聞いていないのだと。
そう、念じながら、後ろに下げた足が、何かに引っかかって。
「……え?」
ヤバイ、と思った時には、身体のバランスは崩れていた。立て直しを試みる間もなく、セイはそのまま川原に引っ繰り返る。川原の石が、衝撃に大きな音を響かせた。
「いってて……」
強かに打ちつけた腰の痛みに顔をしかめつつ、とにかく急いでここを離れなければ、という思いに急かされ、立ち上がろうとした時。
響いていた咀嚼音らしきものが、ぴたり、と止まった。
舞い降りる、重苦しい沈黙。
風が止まり、熱く澱んだ大気と共に圧し掛かるその重圧から逃れたい一心でセイは立ち上がろうとするが、転んだ時にどこか打ち付けたのか、鈍い痛みがそれを阻んだ。
(逃げないと。ここから、離れないと)
何かが意識を急かす。だが、身体は思うように動かない。そんな焦りに囚われていたセイは、座り込んでいた人影が立ち上がった事に気づかず。
「……ちょうだい?」
不意に、投げかけられた言葉に、え? という惚けた声とともに顔を上げ。
「……っ!」
何度目かの息を飲んだ。
いつの間にか目の前に立っていたその女性のまとう、不自然な紅色に。
「……あ……」
年齢は二十代半ば、と言ったところ。元は白かったと思われるスーツは今は黒ずんだ紅に染まり、艶やかな笑みを浮かべる唇は、異様なまでに鮮烈な紅に濡れて。その周囲に漂う独特の匂いは、その紅が何であるかを端的に物語っているかのようだった。
「……ねぇ……ちょうだい?」
呆然とするセイに、女性が再び声をかけてきた。どこか幼い言い回しは、無邪気さすら感じさせる。とはいえ、それは酷く残酷な無邪気さなのだが。
「ねぇったら……ちょうだい、おいしいの」
「お……おいしい、の?」
三度目の呼びかけに、セイはようやくこれだけ返す事ができた。この言葉に、女性はにっこりと笑って頷く。その笑みも、異様な無邪気さを感じさせた。純粋な──透き通るように、純粋な、無邪気さ。善悪概念の未だ身につかない、幼子の微笑み。
「そう……たくさん、必要なの。だから、あなたのも、ちょうだい?」
笑いながらの言葉と共に、女性の視線がす、と下に下がる。彼女がどこを見ているのか、それに気づいた瞬間、セイはとっさにその場所──左胸を手で押さえていた。その様子に、女性はくすくすと声を上げて笑う。鈴を振るような声が、川原を滑って行った。
一しきり笑った女性は、紅に染まった手をゆっくりと上げる。それは緩慢な動きでセイへと伸ばされ、そして。
「……っ! く、くるなよっ!」
手の接近に、セイはそれから逃れるべく、とっさに横へと転がった。川原の石に打ちつけた所が痛むが、それに構っている余裕はないだろう。
セイの動きに、女性はあ、と短く声を上げつつ、小首を傾げて見せた。緩慢な仕種は現実離れしきったこの状況下においても妙に日常的で、それが言葉では言い表せない恐怖感を煽っていた。
「なんなんだよ……なんなんだよ、一体っ……」
じりじりと女性との距離を開けつつ、セイはかすれた声で呟いた。
今、自分がいる空間は。見ているモノは。果たして夢か、それとも現か。
夢だとしたら、今朝のそれと同様──いや、それよりも遥かに質の悪い悪夢で。
でも、夢であるが故に、いつか覚めるという救いもあるのだけれど。
これが現だと──現実だと言うなら、一体何が起きているのか。
わからない。いや、理解などしたくない。
ただ、このままではいけないと。このままでは殺されると。これが夢にしろ現実にしろ、その事だけはやけにはっきりと、鮮烈に理解できていた。
にもかかわらず、身体は思うように動かなかった。本当は走って逃げ出したいのに、そのための力が入らない。ただ、座り込んだままじりじりと後ずさるのが精一杯だった。
紅く濡れた女性は、後ずさるセイの様子にくすり、と笑むと、悠然と距離を詰めてくる。
「……っ!」
募る焦りに急かされるまま、セイは更に距離を開けようとついていた手を大きく後ろに下げた。そして、新たについた場所から手に伝わる感触に、びくり、と身体を震わせる。
「……なっ……」
妙にぬらりとした、生温い感触。セイはとっさについた手の方を振り返り、そして。
「……っ!?」
見なければ良かった、と。そんな考えは、一瞬で、消えた。
いや、そんな事を冷静に考える余裕が一瞬で砕け散った──と、言う方が正しいだろう。目に入った色と、その源。それらは、セイの思考を容易に停止させる。
「……ひと?」
正確には、『かつて人だったモノ』と言うべきかも知れない。胸から腹にかけてを大きく引き裂かれ、紅黒いものを覗かせるそれが生きていたら、それは異常としか言えないだろう。もっとも、既に異常以外の何物でもないこの空間においては、それすらも正常と言えてしまいそうだが。
「そのひとは、くれたのよ?」
とってもとっても、あまかったの、と。その声は、すぐ側から聞こえてきた。はっとして顔を上げれば、無邪気に微笑む女性と目が合う。
「くれた、の、って、言われて、も……」
だからと言って自らも提供しなければらない、という事にはならないはずだ、と。主張しようにも、声が上手く出なかった。緊張のせいか暑さのせいか、酷く喉が渇いていた。
「だから、あなたのもちょうだい? あまいの、ほしいの」
途切れたセイの言葉など気にした様子もなく、女性は幾度目かの同じ言葉を繰り返す。紅く、紅く、美しさすら感じるほどにしっとりと濡れた手が、ゆっくりと伸ばされた。
「……っ!!」
殺される。
そう思った瞬間、身体が大きく震えた。
死にたくない。
浮かんだその言葉に呼応するように、身体の奥で何かが疼く。
死にたくない、死ねない。殺されたくない、殺される訳にはいかない。
ぐるぐるぐるぐる、言葉が意識の内を巡る。
「……いや……だ」
零れ落ちる、かすれた声。しかし、弱々しいそれは緩慢に伸ばされる紅い手を押し止める力にはなり得ず。
妙に冴え冴えとして見える紅は目の前へと達し、そして、その瞬間。
身体の奥でずっと疼いていた『何か』が、大きく、大きく震えた。
……ふ、と。音が途絶える。
無機質に響いていた川のせせらぎも、遠くから微かにかすかに聞こえていた街のざわめきも。音と呼べるものの全てが──自身の鼓動と呼吸の音すらも、刹那、セイの周囲から消え失せた。
舞い降りる、静寂の帳。
その帳の中に、今震えた『何か』の鼓動だけが、響いたような気がした。
(……いけない)
その鼓動は何故か、こんな言葉を意識に浮かべる。
起こしてはいけない。でも。起こさなければ。死ぬ。殺される。
唐突に始まる思考のループは混乱を招き、目の前に達した手、それがびきびきという音を立てつつ形を変え、あり得ない長さに爪を伸ばしていく様子がその混乱に拍車をかけ──。
「う……あ……わああああああっ!」
絶叫が迸り、それを合図とするかの如く、セイの中にずっと施されていた、諸々の『枷』が、一時、吹き飛ぶ。
次の瞬間──音を失った川原に、鋭い風鳴りの音が響き渡った。