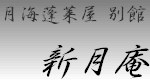
menu
弐 迷える風は荒れ狂い
気がつけば、そこは闇。
周囲には何もなく、誰もおらず。ただ、無機質な黒が立ち込めて。
その色彩から抜け出すべく、歩けど歩けど、しかし、周囲の様子は変わらない。
「……」
心の奥に湧き上がる、不安。それに突き動かされるように走り出す。
しかし、走っても走っても、広がるのは同じ色の闇。
逃れる事などできないのだと。
そう、嘲るように闇はゆらゆらと揺らいだ。
それでも、立ち止まるのは嫌だった。
立ち止まれば飲まれる、取り込まれる──そんな思いが足を前へと進ませて。しかし、変わらない周囲の闇は走っているのかどうかすら曖昧なものとしていた。
そうやって、どれだけ走り続けたのか──不意に、暗闇の中に音が響いた。
「……?」
最初は、空気のざわめきのように思えたそれは徐々にその大きさを増し、何が響いているのかを強引に知らしめてくる。
「……っ!」
響いてくるのが何か、認識した瞬間、身体が震えた。
楽しげな、たのしげな、無邪気さすら感じる笑い声。
楽しそうな口調で、ちょうだい、あまいの、ちょうだい、と繰り返すその声から逃れたい一心で、更に足を速めた。
(いやだ、いやだ、いやだ)
走りつつ、意識はただその言葉を繰り返す。
この闇の中にいるのも、この声を聞くのも、その要求に応える事も、全てが嫌だった。
逃げたい、忘れたい。そんな思いが募れば募るほど、声は近く、大きくなるような気はするものの、しかし、そう念ずる事は止められず。
ただ、ひたすらに走り続けて──不意に足元から響いた、ぱしゃり、という音に足が止まった。
「……っ!?」
反射的に足を止め、今、音を立てたものを見る。見てはいけない、という警鐘が意識のどこかで響くものの、遅く。視界に、黒以外の色が──鮮烈な、紅が映る。
「……う……あ……」
鮮やか過ぎる紅、その色から逃れるように後退りする。いや、逃げたいのはその紅の中央にあるモノ──腕を引き千切られ、胸から腹にかけてを食い荒らされた屍の、ぎょろり、と見開かれた虚ろな眼から、かも知れない。
「み……るな、よ……」
視点がこちらに合う事も視線が交わる事もないはずなのに、こちらを見つめているようなその眼から何とか逃れたくて、じり、と更に後退りした時。
つかまえたぁ、と。耳元に、無邪気な声が零れた。
それと共に、何かが首に絡みつく。ひやりと冷たいそれが何かは、確かめるまでもなく理解できた。
「ね……ちょうだい、あまいの」
笑いさざめくような囁きと共に、左胸に冷たい感触が触れる。
殺される。
ころされる。
喰われる。
くわれる。
意識の内を巡る言葉。それへの、そして、投げかけられた言葉への回答は、唯一つ。
「いや……だ」
ぽつり、零れた声。それに応えるように、身体の奥で何かが揺らめく。しかしその揺らめきもまた、受け入れ難いものに思えた。
「やめろ……」
また、震える声が漏れ、そして。
「頼むから……やめてくれえええええええっ!」
直後に口から迸った絶叫は黒と紅の空間を打ち砕き、真白の光をセイの周囲に呼び込む。
「……あ……」
ベッドの上、文字通り跳ね起きた姿勢でしばし、呆然として。それから、ゆっくり、ゆっくりと周囲を見回す。目に入るのは黒と紅の冷たい空間ではなく、朝の陽射しに彩られた、見慣れた自分の部屋だった。
「……ゆめ……」
小さく小さく呟くのにやや遅れて、携帯のアラームが鳴る。その耳慣れた音は言いようもなく日常的で──強い安堵と友に、微かな違和感をセイに感じさせた。
「……夢……だよ、な。今のも……昨夜の、も」
かすれた声で呟きながらアラームを止める。それは、自分自身に言い聞かせるような響きと、そして、微かな震えを帯びていた。
夢。そう、夢、なのだと。
何度も繰り返す事でそう納得しようとするが、しかし。
自分の中のある一部分は、夢と見なす事を拒んでもいるようだった。
「なんなんだよ……っとに、もう……」
矛盾する心理に苛立ちを感じつつ、セイはベッドから降りて着替えとタオルを用意して階下へと降りて行く。
「……セイ?」
階段を降りるとすぐ、心配そうな声が呼びかけてきた。セイは一つ瞬いてそちらを見やり、
「あ……おはよ、母さん」
声と同じく心配そうな面持ちのトウコに笑いながら挨拶をしていた。笑えるような精神状態ではないのに笑えたのは、いつもの無意識──心配をかけまい、とする思いのなせる業かもしれない。
「顔色、悪いわよ? 夏休みなんだから、少しはゆっくりしなさい」
しかし、さすがにというか母にはその誤魔化しは通じなかった。案ずる面持ちのまま、しかし、口調はやや厳しい言葉を投げかけてくるトウコに、セイはただ苦笑するしかなかった。
「だいじょーぶだよ、母さん。農園のバイトある内はちょっと辛いけど、これ、短期のヤツだし。それに、その内慣れるから」
「……セイ」
「あ……急がないと遅れるから、準備、しちゃうね」
更に言葉を続けようとするトウコににこり、と笑うと、セイは足早に浴室へと向かう。その様子は、その場から逃げるようにトウコには見えて。
「……そんな所は、似なくていいのに……あの子は」
セイの姿が見えなくなると、トウコは小さな声でこう呟いた。
そして、そんな母の呟きもそこにこもる思いも知る由無いセイは浴室に入るとはあ、と大きく息を吐いていた。汗まみれの服は脱いでそのまま洗濯物籠に放り込み、強めに出したシャワーを浴びる。水の勢いに押され、癖の強い髪が普段の勢いを失った。労働系のバイトを多くこなしている事もあり、しっかりと鍛えられている身体の上を水が滑り落ち、汗を洗い落としてゆく。
が──目覚めの夢の感覚は、どうしても拭い去れなくて。
「……何なんだよ、もう……単なる、夢、なのに」
幾度目かの呟きは、自分自身に言い聞かせるような響きを帯びていた。あれは夢なのだと、今朝見たものも、昨夜の出来事も全て、夢に過ぎないのだと。声に出して呟く事で、そう思おうと──思い込もうとするものの。それを阻もうとする何かもまた、自分の中に存在していて。そんな、相反する二つの感覚を持て余しつつ、セイはため息と共にシャワーを止めた。
「……」
唇を噛み締め、水滴のついたタイル張りの壁をしばし、睨むように見つめる。
「夢、なんだから。いつまでも、引っ張られるな、風原誓」
低く呟き、頭を強く振って髪についた水滴を跳ね飛ばす。そうやって強引に気持ちを切り替えると、セイは部屋に戻って身支度を整えた。忘れ物がない事を確かめ、今日の予定を確かめるべく壁に貼ったスケジュール表を見ようと巡らせた視線は、本棚の一角に置かれたフォトフレームで止まった。
フレームに収まっているのは、家族写真。父と、母と、三人で旅行に行った幼い日の思い出を閉じ込めたもの。
「……大丈夫」
僅かな沈黙の後、セイは写真の中の父を見つめながら小さく小さく呟いた。
「オレが、しっかりしないと、ね。母さんを……それから、ミサとユウを、護るためにも」
それがオレの役目なんだから、と呟くと、セイは部屋を出て下へと降りる。キッチンに顔を出すと、昨日と同じくミサが待っていた。
「ごめん、休みなのに早起きさせて」
ちゃんと用意されている朝食と弁当に、さすがに申し訳なさを感じてこう言うと、ミサはううん、と言って首を横に振った。
「あたしは平気……いつもと、変わらないし。それより、セイ……」
「ん……なに?」
サンドイッチを押し込みつつ、セイは妙に不安げな面持ちのミサを不思議そうに見た。
「あんまり無理、しないでね? 昨夜も帰ってくるの遅かったし……帰って来たら、ご飯も食べないで寝ちゃうし。この暑い時期にそんなの続いたら、倒れちゃうからね?」
「あ……うん。わかってる」
真摯な眼差しと言葉に答えようはなく、セイは視線を逸らしつつ早口にこう返すしかできなかった。そんなセイを、ミサは不安げな面持ちのまま、じっと見つめる。
(……なんか、さっきからこんなんばっかり……)
そうなっているのは自業自得以外の何物でもないのだが、何となく愚痴りたい衝動に駆られたセイは心の奥でこんな呟きを漏らす。それでも、それを表層に出すのはぎりぎりで押し止めながらサンドイッチを平らげ、温めのミルクのカップを空にしてからごちそうさま、と言って両手を合わせた。
「ま、うん。夏休み始まったばっかりで倒れる、っていうのも情けないし。そこは気をつけるから、大丈夫」
それから、ごく軽い口調でこう言って笑って見せる。ミサが言っているのはそういう事ではない、というのは、セイ自身にもわかってはいるのだが。
「もう! そういう問題じゃないでしょ?」
案の定、怒ったような声を上げるミサの様子にあはは、と笑って誤魔化しつつ、セイは弁当を手に取ると、いってきまーす、と言って外へと逃げた。これ以上この事で問答をしていると遅くなりそうだし、何より、あまり話したくない事まで話させられそうで怖かった。
「……ほんとに……もう……」
セイに時間がないのはわかっていたから強く引き止める事こそしなかったものの、ミサとしては言いたい事はまだまだあった。帰って来たら、今度こそ、と決意を固めつつ、ミサは食器を片付け始める。それと前後するように、居間のテレビが失踪事件のニュースを伝え始めた。ミサは一度手を止めて、画面の方へと視線を向ける。
ここ数日、立て続けに起きている連続失踪事件。失踪した者は年齢も性別もばらばらで、事件なのか事故なのか、それすらも未だわかってはいない。そんな事件にセイが巻き込まれはしないだろうか、と。そう考えると気が気でないミサなのだが。
「なのに……暢気なんだから」
一見するとお気楽そのものなセイの態度を思い返して、ミサは小さくため息をつく。肉体的には元より、精神的にもセイが疲労しているのは察しがついていた。にも関わらず、当のセイは掴み所のない態度を崩そうとせず、それが、ミサにはもどかしかった。
「もう少し、頼ってくれればいいのに……」
小さな小さな声でささやかな願いを呟いて、テレビを消す。消される直前のテレビには丁度、新たな失踪者の顔写真が映されていた。ミサにとっては、全く知らない男女──だが、セイが未だここにいて、その写真を見ていたなら。そうなっていたら恐らく、酷く動揺した事だろう。
画面に映し出されたのは、セイにとっては『ついさっき』見た顔──『夢』に出てきた二人の写真だったのだから。
しかし──幸いにというか、セイはそれを目の当たりにする事はなく。
「ふうっ……今日も、暑くなりそ」
ガレージから自転車を引っ張り出しつつ、空を仰いで暢気な呟きを漏らしていた。見上げた空は今日も晴れ渡り、気温が上がって暑くなる事を示唆している。頭上に広がる澄んだ青色、それに思わず嘆息していると、
「……セイ!」
庭の方から名を呼ぶ声と駆けて来る足音が聞こえて来た。え? と言いつつ振り返った先には、憮然とした面持ちのユウが立っている。
「ん? どーした、ユウ」
軽い口調で問いかけると、ユウはセイに駆け寄り唐突に鳩尾へと拳を突き入れてきた。決して軽くない衝撃にセイは思わずよろめく。
「ちょ、ユウ、いきなり……」
「お姉ちゃんに、心配かけるなよな!」
いきなり何すんだよ、と問うより早くユウは低い声でこう言って睨むように見上げてきた。この一言にセイは反論を飲み込んで口ごもる。ミサに心配をかけているのは感じているだけに、ユウの言葉は痛かった。
「わかってるよ……これから、気をつけるって!」
飲み込んだ反論の代わりにこう言って、セイはぽむぽむ、とユウの頭を撫でるように軽く叩く。叩かれたユウは、不満げな様子で頬を膨らませた。
「子供扱いするなよなっ! ……三つしか、違わないんだからっ!」
「はいはい、わかってるわかってるって」
ユウの主張にセイは苦笑しながら頷くものの、頭の上に手が乗ったままでは説得力がない。
「とにかく、留守の間は、頼むぜ? 頼りにしてんだから」
「……言われなくても、わかってる」
一転、やや真面目な口調になったセイの言葉に、ユウはまだ憮然としてはいたものの、こう言って頷いた。『頼りにして』という言葉はやはり、まんざらでもないらしい。セイは任せたぜ、と言いつつもう一度ユウの頭を軽く撫でると、道に出した自転車に跨る。
「んじゃ、行って来ます、っと!」
勢い良くこう言うと、セイは夏の大気の中へと一気に漕ぎ出した。風は熱いが、そのからりとした感触は心地よい。
勢いをつけたメタルブルーの車体は、すぐに揺らめく大気の向こうに消え、後にはユウが一人、残される。
「……子供扱い、するなって言うのに……」
既に見えなくなったセイに向け、ユウはもう一度、その言葉を繰り返した。やや俯いたその表情には僅かに陰りめいたものが浮かんでいたが、それを見る者はない。ユウは一つため息をつくと家の中へと戻って行き、熱い大気の揺らめく住宅街の通りは気だるい静寂に満たされた。
風の通りは決して悪くはないが、夏の日中は人通りの少ないその道に、不意に、黒い影が揺らめく。
「…………」
黒のシャツとジーンズの上から同じく黒の、ややオーバーサイズ気味のロングコートを羽織り、足回りまで御丁寧に黒のブーツで揃えたまだ若い男──外見的には十六、七歳の少年と言えそうだが、その視線の鋭さと妙に板につくくわえ煙草は外見通りの年齢には似つかわしくはない。そして、一本に束ねられて黒のコートの上にさらりと流された銀色の長い髪は、どこか現実離れしたものを感じさせた。
「……ふうん……あいつ、か」
突然、どこからともなく現れた男はしばしセイの走って行った方を見つめていたが、やがて煙草を落として小さく呟いた。
「覚醒しかけの、強い力……あのままにしとくのは、色々とヤバイ、な」
呟きはここで、どこか大げさなため息に遮られる。落とした煙草をブーツで踏み消し、吸殻を拾い上げると、男はもう一度セイの向かった方を見た。
「眠れる風……アレのエサになられても、ヤツに取り込まれても不都合……か。やれやれ、めんどーな」
吐き捨てるような口調でこう言うと、男は踵を返して歩き出す。程なくその姿は夏の揺らめく大気の向こうへと消え、住宅地には再び、気だるい静寂が舞い降りた。
「しっかし、あっちぃ〜……」
「文句ばっかり言うなって」
今日も変わらず暑いハウスの中に、妙にぐったりとした声と呆れようにそれを諌める声が響く。ぐったりとした声の主はタカユキ、諌める声の主はセイだ。
「にしたって、暑いと思わね? っつーか、暑すぎるって、ここ」
「まあ、暑いとは思うけど……仕方ないじゃん、夏のビニールハウスの中なんだし。こんなもんなんじゃない?」
軽い口調で言いつつ、セイは運び出しを頼まれた野菜の苗を持ち上げる。タカユキはそうだけどさ〜、と言いながら、行儀良く苗の並ぶ黒いプラスチックのケースを持ち上げた。
「っつーか、セイが平然としすぎなんだと思うんだけど」
「そぉ?」
「うん、妙に涼しげだし」
「……気のせい、気のせい」
タカユキの突っ込みにごく軽く返しつつ、セイはビニールハウスの外に停められたトラックへと苗を運んでいく。瑞々しい緑を荷台で待つ職員に渡したところで、セイはふう、と一つ息を吐いて空を見上げた。
夏の晴天。澄み渡る青空に熱い風。
ごく当たり前の夏の空は、妙に強い安堵を感じさせた。
「……セイー?」
一歩遅れて出て来たタカユキが、空を見上げて立ち尽くすセイの様子に訝しげな声を上げた。どうかしたのか、と言わんばかりの表情に、何でもないよ、と笑って返すと、セイは次の苗を運ぶべくハウスへと戻る。
平凡で当たり前で、平穏平和な日常。
いつもなら何という事もなく感じているそれらが、今は、言いようもなく心地よかった。
(そう……何にも、おかしい事なんて、ないんだ)
苗のケースを持ち上げつつ、セイは心の奥でこう呟く。
変わっていない。何も、変わってなどいないのだ、と。そう、自分に言い聞かせるように。
(何も、変わってない。変わらない。オレは、オレのまま……)
幾度目か、そう繰り返したその時。
「ニュース、見たか?」
「ああ……田崎さんのとこの……だろ?」
「行方不明、だっけ?」
少し離れた所で、職員たちが話している声が耳に届いた。
「……ようやく、身を固める気になった、って喜んでたのになぁ……」
「昔の恋人も、行方不明なんだってねぇ……」
話題になっているのは、今日は休んでいる年配の職員の身内の事らしい。特に気にするような事でもない──そう考えたセイは、再びハウスの外へ向かおうとするが。
「事故だか事件だかに巻き込まれたって話だけど、どうなのかねぇ」
「最近、行方不明多いし……確か、そこの河原で血痕が見つかったんだろ? この辺りも物騒になったもんだ……」
聞こえて来た言葉に、知らず、動きが止まった。
(河原……血痕?)
二つの言葉、それは容易にあの『夢』を呼び起こす。
紅に沈んでいた男の姿。
虚ろな眼。
絡み付くような声と、冷たい感触と──。
「……セイ?」
蘇る『夢』に強張っていたセイの意識を、不意の呼びかけが現実へと引き戻す。呼びかけ、というよりは直後に肩に触れた手の感触が、というべきかも知れないが。触れてきたのは『夢』の中のそれとはまるで違う、ごく当たり前の温もりを帯びた手だった。にもかかわらず、それはあの冷たさを思い起こさせ、そして。
ヒュっ、と。短い風鳴りが、大気を震わせた。
その音にはっと振り返ったセイは、目の前に舞う紅に息を飲む。
「あ、あれ……?」
「……タカっ!」
それが何か、どこから散ったか、一瞬理解が追いつかなかった。追いつかせたくなかった──というべきかもしれないが、今のセイにはそれに気づく余裕はない。
「て、ちょ、何だこれっ!? 手、切れて、え、え?」
タカユキが動揺しきった声を上げる。何の前触れもなく伸ばした手の甲が裂けて血がしぶいたのだから、動揺するのも無理はないだろう。セイは持っていた苗のケースを取り落とし、首にかけていたタオルでタカユキの手の傷を押さえる。セイとタカユキ、双方の手から投げ出された苗は小さなポットごと、或いはそこから零れ落ちつつ、二人の周囲に散らばった。
「セ……セイ?」
突然の事に驚いたのか、タカユキがどこか呆けたような面持ちで名を呼ぶが、セイはそれに答えなかった。
紅い色彩は見たくない。
とっさに考えたのは、それだけだった。
勿論、友の怪我を案ずる気持ちも強いが、それよりも、それ以上に。
紅は──血の色彩は、見たくなかった。
押し当てたタオルが血を吸い、その色彩を浮かび上がらせる。その頃には、二人の様子に気づいた職員たちが周囲に集まってきていた。
「一体、どうした?」
「それが、あの……突然、手が切れて」
職員の問いに、タカユキは自分の手と、そこを押さえつけるセイを見てから困惑の滲む声で状況を完結に説明する。
「突然、手が?」
「かまいたちでも起きたか?」
「とにかく、医務室で手当てを。風原君、ここはいいから長沢君と一緒に……風原君?」
タカユキの説明に職員たちは不得要領、と言った面持ちで言葉を交わし、その内の一人が足元に散らばった苗とタカユキの手を見比べながらセイに声をかけてきた。その声に、傷口を押さえつけるのに集中していたセイははっと顔を上げてそちらを見る。
「あ、は、はい……なに、か?」
上擦った声での返答は場の状況からは大分ずれていて、それは周囲に困惑を呼び込む。タカユキも職員たちも怪訝そうな面持ちでセイを見つめ、向けられるその困惑を、セイ自身も困惑で受け止める。
「セイ……お前も、大丈夫か?」
タカユキがいつになく真面目な面持ちで問うのに、セイはうん、と頷いた。
「タカの方が、大変、だろ。手当て、しないと」
それから、途切れがちにこう告げるこの言葉にタカユキは怪訝そうな面持ちのまま、ああ、と頷いた。
「でも、セイ……お前、ほんとに大丈夫かぁ?」
確かめるような問いにセイはタカユキの手から自分の手を離して、うん、と頷く。手を離すとタオルに滲んだ紅が目に入り、セイはとっさにその色彩から目を逸らしていた。