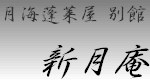
menu
壱 眠れる風は夢をみる
夢を見た。
夢の中で自分は笑っていた。
笑いながら……人を、殺していた。
黒一色の世界に舞う、真紅。
人の手足が、ツクリモノのように飛ぶ。
それが──その行いが楽しいのか、それとも狂っているのか、それは定かではないものの。
舞い、飛び散るそれらを自分は楽しげに。
とても、楽しげに笑いながら、見つめ。
そして新たなそれを求めるかのように、違う誰かを引き裂いた。
夢。
ただの夢であってくれ、と叫びたくなるような、凄惨な紅。
何とかして、そこから逃れたかった。
黒と紅の凄惨さと、そして何より。
明らかに状況を楽しんでいる自分から、何とかして逃れたくて──。
止めてくれと、そう、願ったその時。
軽快なメロディが意識に飛び込み、目覚めの光を呼び込んだ。
「……っ!」
メロディに呼び戻されるように目を開ければ、目に入るのは見慣れた天井。
カーテン越しに差し込む日差しを映したそれをぼんやりと見つめつつ、セイは呼吸を整えた。
「……夢」
掠れた呟きが零れ落ちる。
夢。この短い言葉で済ませるには、余りにもリアルな色彩を伴ってはいたが、しかし、だからと言ってあれが現実なはずはなかった。現実だとしたら、幾らなんでも大問題だろう。
「……疲れてんのかなー……」
タオルケットを足元に蹴飛ばしつつ、ゆっくりと身体を起こす。汗でべったりと貼り付くTシャツの感触に顔をしかめつつ、セイは歌い続ける携帯を手に取り、目覚まし代わりのアラームを切ろうとして──。
「て、いうか……やば、急がないと遅れるっ!」
自分の現実を思い出した。
夏休みに入り、短期のバイトを一つ増やしたのは昨日の事。そしてこのままのんびりとしていると、明らかにそれに遅刻する。初日から遅刻はまずい。かなり、まずい。
「……やっべ!」
焦りを帯びた声で言いつつ、セイはアラームを止めた携帯をサイドボードに置いた。遅刻はまずい、という意識に急かされるまま、着替えとタオルを引っ掴んで部屋を飛び出し、シャワーを浴びに行く。
幸い風呂場には先客はなく、セイはすっかり汗ばんだ服を洗濯物入れに投げ込み、温めの温水を勢いよく出して絡みつく汗を洗い落とした。それと共に、目覚めの夢をも押し流したい、と、ふとそんな事を考えながら。
シャワーを止め、頭を左右に振る。水滴と、意識の奥に絡みつく黒と紅をそれで強引に振り落とすと、セイは部屋に戻って身支度を整える。
「さってと……気合入れて、行くか!」
立てた左の掌に右の拳を打ち当てながら低く呟き、気合を入れるとセイは部屋を出る。時間的にゆっくりはできないが、やはり何か食べてから……と思ってキッチンを覗くと、待ち構えていたかのようにサンドイッチの乗った皿が目の前に差し出された。
「え……ミサ?」
「ゆっくり食べなきゃダメ、って言っても、『時間ない』って言うでしょ?」
思わず惚けた声を上げると、サンドイッチの向こうからちょっと困ったような笑顔が向けられた。トレイを手にしたミサの、黒目がちの大きな瞳にはほんとにもう、と言わんばかりの光がある。その表情と言葉に、セイは決まり悪い物を感じつつ、うん、と頷いてサンドイッチを一つ手に取った。
できるならゆっくりと味わって食べたい所なのだが、今は仕方ない、と押し込むように平らげていく。そんなセイに僅かに心配そうな視線を向けつつ、ミサはタイミングよくミルクの入ったマグカップを差し出してくれた。
「ん、さんきゅ」
幼馴染のそんなちょっとした気配りが嬉しくて、セイは笑いながらカップを受け取る。何も知らない第三者がこの光景を見たなら、新婚夫婦と勘違いしかねないくらい、二人の様子には違和感と言うものがない。
勿論、そんな指摘をしようものなら二人同時に反論してくるのだろうが。違和感がないのは単にこの状況を長く続けているからなのだと。
確かに、それぞれの家庭事情から同居するようになって七年、ミサがセイの母・トウコに代わって家事をするようになってから四年。時間的には、馴染んでいてもおかしくはないのだろうが。
「あと、これお弁当ね。お昼はちゃんと、ゆっくり食べなきゃダメよ?」
ほんの少しだけ厳しさを帯びた口調で言いつつ、ミサは小さなバスケットを差し出してくる。セイははいはい、と言いつつずしりと重いそれを受け取り、空になったカップをミサに渡した。
「あ、それと、帰り遅いなら気をつけてよ? 最近、行方不明とか、そういう嫌なニュース多いし……」
「わかってるって、大丈夫! んじゃ、行ってきまっす!」
心配そうなミサに明るくこう言うと、セイは外へと走り出す。自転車の前かごにバスケットを入れ、ふと、空を見上げる。
「……本日、快晴、っと」
広がる青空、その色彩に不思議な安堵を感じつつ、セイは少しずつ暑さを増していく夏の大気へと飛び出した。
その一方で。
「……セイ、でかけたの?」
家の中では、今起き出してきたらしいユウがミサにこう問いかけていた。ミサは弟を振り返り、ええ、と頷く。
「また、バイト増やしたんですって」
夏休みなのに休まないんだから、と、呆れたように呟いた後、ミサは異様に眠そうな様子で欠伸を繰り返すユウに僅かに険しい視線を向けた。
「ユウ〜? あなたも、ちゃんと寝てる? 夏休みだからって、夜更かししないの!」
こつん、と軽く頭を小突きながらの言葉に、ユウは首をすくめてごめん〜、と呟いた。
「ほんとにもう……さ、顔洗ってきなさい。朝ご飯にしよ? あ、トウコおばさまに声、かけてね?」
こう言うとミサはキッチンへと戻り、窓から差し込む日差しに眩しそうに目を細めてから、用意していた朝食を食卓へと運んでいく。どこかリズミカルなその動きにあわせるように、深い藍色のリボンで一本にまとめた長い黒髪がふわりと揺れた。
一方のユウは眠そうに顔を擦りつつ、大きな欠伸と共にはぁぃ、と返事をして言われた通りに顔を洗いに行く。
彼らにとってはごく当たり前の、日常風景。
七年前、セイ──風原誓の父とミサとユウ──天野美沙・悠姉弟の両親が原因不明の事故で亡くなり、他に身寄りがない姉弟が自立できるようになるまで、とトウコが二人を引き取って以来、これが彼らの『日常』となっていた。
セイはバイトで家計を支え、ミサは外で働くトウコの代わりに家事をこなし、ユウがそれを手伝う。
それは決して一般的とは言えないものの、しかし、当事者たちにとってはごく穏やかな日常であり、そして。
セイにとっては何よりも大切な──『護るべき日常』であると言えた。
「……いよっと!」
掛け声と共にハンドルを切り、勢いをつけて車体を弾ませジャンプ。少しでも時間を稼ぐため、土手に沿った九十九折の坂道をそれでショートカットする。よほど上手くやらなければ簡単にバランスを崩して転倒してしまうであろうそれを、セイはいとも容易くやってのけた。
飛び上がったアスファルトに再び戻った自転車は、がしゃん、と音を立てて大きく揺れる。伝わる衝撃が、クセの強い髪を揺らした。しかし、濃いメタルブルーの車体は何かに支えられているかのように安定を維持し、残りの坂を軽快に下っていく。
吹き抜ける風の感触が、心地良い。
その感触を楽しみつつ下の通りへと下り、郊外方面へしばらく走れば新しいバイト先──市営農園にたどり着く。
「セーイっ! 遅いっての!」
農園の門を潜り、自転車置き場に滑り込めば聞きなれた声が耳に届く。セイにここでのバイトを教えた──というか、セイを巻き込んだ張本人、クラスメートのタカユキだ。
「ごめっ! これでも、飛ばしてきたんだぜー?」
自転車の前輪を整列用のフレームに乗せてロックしつつ、セイはこう返す。
タカユキはそりゃそうだろうけどよ、と言いつつ黒の前かごから取り出されるバスケットをじっと見た。
「……なんだよ?」
タカユキの視線に気づいたセイは、一つ瞬きつつ不思議そうにこう問いかけるが。
「いや……なんでも?」
タカユキはにやにやと笑いつつ、こう返すだけだった。とはいえ、あからさまに含みのある態度はその言葉を額面通りには受け取らせず、セイはなんだよ、と更に問いをついだ。
「いや、ほんと、何でもないってー? たださー」
「ただ……なに?」
「いいなあ、と思って。愛妻弁当」
「……え?」
にやにやと笑いながら、さらりと言われた言葉。セイは一瞬、その意味を掴みあぐね、そして。
「なっ……ターカーっ! お前、なに、言って!」
理解した瞬間、大声を上げていた。タカユキは照れるな照れるな、とにやついたままそれを受け流す。それにセイが更に反論しようとするのを遮るように、
「おーい、そこのバイト生二人! いつまで遊んでるんだ、早く準備してハウスに集合しなさい!」
やって来た職員が声をかけてきた。二人はぴたり、と動きを止めた後、すいませんっ! と声をそろえて頭を下げる。
「よし、んじゃ気合入れて行くか!」
「セイ、元気だなぁ〜……とにかく行こうぜ、ロッカーこっち」
意気を上げるセイに、タカユキはやや呆れたようにこう言って歩き出す。
「元気なくして、家計は支えられません、ってね!」
それにさらりとこう返しつつ、セイはタカユキに着いて行く。
ごく、当たり前の。ごく、普通の。日常。
慌しくもどこか穏やかなそれは、目覚めの夢の鮮烈な紅を忘れさせてくれる。
夢──確かにあれは、夢なのだろうけど。
「ふう……あっちぃ……」
首からかけたタオルで汗を拭い、一つ息を吐く。額の濡れた感触が一時取れると、セイはスポーツドリンクのミディペットの口を開けてその中身を流し込んだ。
ただでさえ暑い夏の日に、蒸し暑いビニールハウスの中で作業していればどうなるかは自明の理、1リットルのミディペットではすぐに足りなくなりそうだった。
「明日っからは、水筒持ってきた方が得かも……」
などと呟きつつボトルのキャップを閉め、作業を再開する。主な仕事は、畝の草取り。収穫作業が一段落したら、その運搬もあるらしい。短期で高収入のわりに人がいないのは相当きついからかな、というセイの予想はしっかりと当たっていたようだった。
それでも、セイ自身は身体を動かす事は嫌いではなく、こういう土や植物と接する作業は好きな方なので、わりと楽しみながら作業をしていた。少し離れた所で辛そうに作業をするタカユキに、しっかりしろよー、と声をかける余裕すらある。
「にしても……あっちぃ……」
引き抜いた草をかき集めて集積場へと運びつつ、熱い息と共にこんな呟きをもらす。先ほど摂った水分も、既に身体の中にはないような、そんな気すらしていた。
(ハウスん中だし、仕方ないけど……もうちょい、風でもあればなあ……)
それが無理な相談なのは百も承知なので声に出しはしないものの、ハウスの中の熱気にふと、心の奥にこんな愚痴がこぼれ──その、直後。
「……え?」
ふ、と。風が周囲を吹き抜けたような、そんな気がした。風は火照った身体の熱をふわりと浚い、一時涼しさを呼び込む。
「……あれ?」
一瞬の、あり得ない現象。思わず呆けた声を上げて周囲を見回すが、作業中の他の面々の様子に変化はない。
「……気のせい?」
それにしては、確かに身体は冷えているのだが。しかし、そんな不可解な現象に首を傾げていられるほど今は暇ではなく。
「あーと、バイト生の……長沢くんと、風原くん! そっち一段落させて、こっちの方手伝って!」
ハウスの入り口の方から聞こえた声が、思考を現実へと引き戻す。セイは軽く頭を振ると、わかりましたぁ、とそちらに答えた。タカユキも、わかりましたぁ〜、と返事をしているが、こちらが疲れきっているのは声だけでも十分に伝わってきた。
「タカ、無事かー?」
その声にくすり、と笑みをもらしてからこんな声をかけ、抱えた草を集積場へと運んで行く。
その後に続くように風が揺れた事には、今度はセイ自身も気づく事はなかった。
「うへ〜……疲れた……」
そして、昼時。冷房の効いた休憩室の隅に落ち着くなり、タカユキはこう言ってテーブルに突っ伏した。
「情けないなあ……初日からそんなんで、やってけんの、一週間?」
その様子に、セイは呆れたようにこう突っ込む。
「情けないって、お前は平然としすぎたろ、セイ」
それに、タカユキは身体を起こしつつこう返してくる。セイは弁当の入ったバスケットを開けつつ、そうかなあ? と首を傾げた。タカユキは真顔でうん、と頷きつつ、売店で買って来たサンドイッチの包みを開ける。
「確かに、きついって言えばきついけど……」
おにぎりと、おかずの入ったタッパーをテーブルに並べつつ、セイはかりり、と頬を掻く。作業労働系のバイトもそれなりに経験があるせいか、さほど辛いとは思ってはいなかった。
「でも、きつい分実入りは良いんだし。市民温泉のタダ券ももらえたし。悪くないと思うんだけどなー?」
おにぎりを一口かじってこう言うと、タカユキは確かにそだけど、と返してサンドイッチにぱくりと噛み付いた。
「でも、おまけが温泉のタダ券ってのも……プールの方が嬉しかったかも」
「……タカ、それ問題違う、きっと」
ぶつぶつと文句を言うタカユキに、セイは呆れを込めてこう突っ込む。温泉のタダ券は結局、汗を流してさっぱりしてから帰れるように、という気配りによるものなのだから。
セイのようにこの後も別のバイトが控えている身にはありがたいのだが、家に返ってシャワーを浴びれば事足りるタカユキにはさしてありがたくはないのだろう。
「いや、わかってっけどさー……って、セイ。お前、これからまたバイト?」
大げさなため息をついた後、タカユキはふと気づいたようにこう問いかけてきた。
「うん、今日はあと二件」
それに、セイはさらりとこう答える。二件、という返事に驚いたのか呆れたのか、タカユキはうげ、と呻くような声を上げた。
「お前、働きすぎ。ちゃんと休めよ〜、ミサちゃん心配してるぜ〜?」
「うん……って、なんで、お前がそんな事知ってるんだよ?」
何気なく相槌を打ってからふと疑問を感じて問うと、タカユキはにやり、と笑った。
「さぁて、なんでだろ〜? ……って、じょーだん、じょーだんっ!」
へらへらと笑うタカユキにセイは睨むような視線を向け、それに気づいたタカユキは口調を切り換えてぱたぱた、と手を振った。
「ミサちゃんは、チカとかアユちゃんに相談してるみたいだぜ? で、チカ経由でそういう話がオレんとこに回ってくんの」
説明を終えたタカユキは、おわかりぃ? と言いつつまたにやりと笑う。セイはどう答えたものか悩みつつ、取りあえずふわりとした黄色の玉子焼きを箸で挟んで口に入れた。ほんのりとした甘味が、口の中に広がる。
「ま、お前もイロイロと大変なんだろうけどさ〜」
あんまり無理すんなよ? と。そう言って笑うタカユキに、セイはうん、と頷く。
「それとさ、八月、どっかスケジュールあけとけな? クラス有志で、海水浴と花火大会やろーぜって計画あるからさ」
「八月? ん〜、開けられるかなあ……」
「開けられるかな、じゃなくて、開けろ。こっちはそれに合わせるから」
「別に、オレに合わせなくても……あいてっ!」
合わせなくてもいい、という言葉は、べこん、という鈍い音と衝撃に遮られた。
「そういう、サビシイコト言うなよ、お前はっ!」
今の音の源──中身の半分残ったペットボトルを手にしたタカユキは、呆れたような、それでいてどこか怒ったようにこう言い放つ。セイはペットボトルで殴られた所を抑えつつ、きょとん、と一つ瞬いた。
「タカ……」
「ったく、お前、高校の思い出バイトオンリーにする気かよ? いや、お前ん家が大変なのは知ってるけど……剣道も、止めちまうしさ」
ぶつぶつと言うタカユキはどこかつまらなそうな、寂しそうな、そんな感じがして。セイは苦笑めいた笑みを浮かべて、ごめん、と呟く。
「ちなみに、剣道は止めてないよ? まあ、部活入ってないし、道場にも顔出してないけど、稽古はしてるから」
「なら、いいけどさ〜……」
ため息混じりのタカユキの言葉に、セイはかりり、と頬を掻いた。小学校の頃から同じ剣道場に通い、抜きつ抜かれつをしてきたタカユキとしては、ライバルとみなすセイとの差がつくのが嫌なのだろう。
「時間できたら、また道場にも顔出すって! ……さって、そろそろ行かないと、次、間に合わなくなるから、オレ、行くよ」
空になったタッパーやおにぎりのラッピングをバスケットの中に片付けつつ、軽い口調でこう言うと、タカユキは絶対来いよ? と念を押してきた。セイははいはい、と頷いて立ち上がる。
「んじゃ、また明日な?」
「ああ、明日は遅れんなよー」
「わかってるっての! んじゃ、お疲れ様でした、お先失礼しまーすっ!」
突っ込みタカユキに苦笑を向けると、セイは休憩所にいた他のバイトや職員に挨拶をして外に出る。外に出ると、夏の日差しが風が熱気を孕んで出迎えてきた。
「ふぅ……あち」
小さな声で呟きつつ、自転車置き場へと向かう。その後を追うように、ふわり、と風が吹き抜けた。