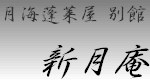
menu
ゆら、と。桜の周囲で、不自然に大気が揺れる。
その瞬間、全ての音が、途絶えた。
音の途絶えた空間に響くのは、ざわり、という葉擦れの音。青々と茂っていた桜の葉が風もないのに大きく揺れ──直後に、枝を離れて天へと舞い上がった。
葉が舞い上がった後の桜の枝に残るのは、季節外れについた蕾のみ。それはゆらり、と揺れた後、その花弁をゆっくりと開いて行き──開ききるのと同時に、リン、という澄んだ音が空間に、落ちた。
「……な、なんだ、今の……?」
「鈴の音……?」
場にいる全員の耳に届いた一音と、唐突な異変と。それらに対する困惑がざわめきとなって広がっていく。そのざわめきを制するかのようにまた一つ、鈴の音が響き、そして。
「……さくら、さくら……」
どこか幼さを感じさせる少女の声が、中央公園に響き渡った。
「いのちのまつり。
おもいのめぐり。
きみゃくはめぐる、ちからのままに。
きざめ、きざめ、いのちのしるし。
ゆくかいなかはだれもしらぬよ。
さくら、さくら。
はなはひらきてみまもるのみ。
さくら、さくら」
稚い声は、古風な節回しで歌を紡いで響かせる。その歌に応ずるように桜の枝がまた、揺れて、そして。
「……っ! ダメ、だっ……!」
枝の揺れる様に、セイは知らず、こんな言葉を口走っていた。
桜を咲かせてはいけない、桜が咲いたら、『始まって』しまう。
そして、『始まって』しまったら──もう、逃げられない。目を背けてはいられない。
だから、と、紡がれた祈りを嘲るように桜の枝は揺れて──高く大きく響く鈴の音と共に、薄紅色が弾けた。
「……あ……」
宵闇色に染まった空に、薄紅の花弁が舞う。
夏の色を宿した夜空を背に、春の花が咲き誇る。
在り得ないいろ、在り得ない光景──なのに、そのいろと光景には覚えがあった。
「……これ……って……」
掠れた声が、零れ落ちる。唐突な出来事にざわめく周囲の喧騒も、今のセイには全く届いてはいなかった。呆然と見開かれた瞳は満開の桜へと向けられている。
(オレ……知ってる? 同じように、咲いた、桜……)
(……あの時の桜は、これより、もっと、小さかった、けど)
夏の夜空を背にした満開の桜──今よりずっと視点が低かった頃に、確かにそれを見上げた。薄紅を揺らす枝と、その前に立つ人を──。
「……っ!」
何の前触れもなく、頭の芯に痛みが走る。同時に過ぎるのは、『思い出してはいけない』という思い。思い出したら、本当に戻れなくなる──と。そんな怯えが身を震わせたのは、僅かな時間だった。
「……きゃあああああっ!」
唐突に響いた悲鳴が、セイの意識を現実に引き戻す。声の聞こえた方へと目を向けたセイは、ほんの一瞬見えたいろ──鮮烈すぎる紅色に息を飲んだ。
「なに、いま、のっ……!」
呆然と呟く声に重ねるように、
「な、なんだよ、どうしたんだよっ!」
「ば……化け物っ!?」
「ちょ、く、くるなあああっ!」
絶叫と悲鳴が中央公園のあちこちで上がり、それと共に紅い色が飛び散り始めた。混乱が広がり、中央広場にいた野次馬たちは我先にとその場から逃げ出していく。それによって開けた視界に、それは真っ向、飛び込んできた。
「……っ! あれ、はっ……」
紅い色を浴びて、薄く笑う者。紅く濡れた手の先には歪な爪が伸びている。その爪も、笑みも、纏う気配も、全て、覚えのあるものだった。あの日、河原で見た女と全く同じ──『憑魔』のもの。
「……あ……」
始まってしまった、と。そんな言葉がふと、過ぎって、消える。そしてその事実に向き合うよりも僅かに早く、
「セイ!? そこにいるの、セイかっ!?」
聞き慣れた声が名を呼んで、セイの意識をそちらに引き寄せた。振り返った先にはタカユキの姿がある。セイは数度瞬いた後、そちらへ駆け寄っていた。
「……逃げて、早く!」
駆け寄るなり、口をついたのはこんな言葉だった。
「い、いや、逃げるったって……」
唐突に起きた出来事に混乱しているのか、タカユキの返事は上擦っていた。それも無理はないだろう。唐突な桜の開花だけならまだしも、突然始まった流血沙汰に混乱しない方がどうかしている。
「今なら、まだ、間に合うからっ! 早く、ここから……桜から、離れろ!」
だからと言って、タカユキをここに止まらせるわけには行かなかった。このまま桜の近くにいたら、本当に逃げられなくなるから。だから、何とかしてこの場から離さなくては、との思いに駆られたセイはその時、すぐ近くに『憑魔』がいる、という事を完全に失念していて。
「……っ!? セイ、う、うしろっ!」
タカユキの絶叫に振り返った時には、『憑魔』はすぐ側まで迫っていた。歪に伸びた爪が、緩慢な動作で振り上げられる──セイはとっさにタカユキを突き飛ばしつつ、左腕を頭を庇うように翳していた。
「……セイっ!?」
タカユキの声が名を呼ぶ声に、風が周囲に渦を巻く、ヒュウ、という音が重なる。
それと前後するように、紅が、散った。
「っだあああ、っとにめんどーなっ!」
宵闇色の空を背に揺れる薄紅。その色に、シオンは苛立ちを隠す事無くこう吐き捨てていた。
「よりによって、こんな大量の野次馬のいる状況で始まるかよっ……! 二重三重に厄介じゃねーかっ……!」
人が多いという事は即ち、『憑魔』となり得る者の数が多い、という事に繋がる。シオンにとってそれは、多重の意味で歓迎できる事ではなかった。『憑魔』を闇に還す『司』としての務め的な意味は元より、それとはまた違う厄介事にも繋がるからだ。
「……まだ、『護界』は完全に形成されてねぇか……それなら、一人でも多く……」
桜の力の及ぶ範囲から引き離す、と。言いかけた言葉は途中で途切れた。
「一人でも多く、どうすると? 逃す、というのは例えお前でも許さぬよ……愛しき『水牙』」
不意に耳元に落ちた囁き声と、するり、と首に絡み付いてきた腕。そして、自らのそれと相反する力。三つの要素が一瞬、シオンの思考を停止させる。一呼吸分の間を置いて肩越しに振り返ったシオンは、愉しげに笑う口元と血を思わせる紅の瞳をそこに認めて表情を強張らせた。
「……氷霧!」
鋭い声と共に、シオンの右腕を氷の霧が覆う。力を纏った腕で繰り出した全力の肘打ちは、当たる直前に対象が距離を取った事で空を切った。シオンはそのまま前へと跳んで更に距離を開け、先に地に着いた右足を軸にくるり、身を翻す。
「……ショウ、てめぇ、いつの間にっ……!」
距離を取って相対する形となった男へ向けるシオンの声は低く、蒼い瞳にセイと向き合っていた時の余裕は見られない。そこにあるのははっきりそれとわかる苛立ちと、そして、嫌悪の色だった。
「いつの間にも何も……お前のいる所に、我は在る、と。そう、言っておいたはずだが?」
対する男──ショウ、と呼ばれた真紅の装いの男の紅の瞳にあるのは、余裕。それと共に慈しむような色もまた、そこに浮かんでいた。
「……いい加減にしろ、この変態ストーカー」
滲む嫌悪を隠す事無くこう言い放つと、シオンはショウとの距離を測る。ここで時間を取られるわけにはいかないのだが、容易く振り切れる相手ではない、というのもわかっていた。それだけの力が目の前の男──真紅の髪と瞳、そして装いに違わぬ焔の力の持ち主にはある、と。そう、認識しているからこそ、手を抜く事はできない。
「口の悪さは、相変わらずだな……まあ、いい。それがお前の可愛らしさの一つでもある」
そんなシオンの緊張を知ってか知らずか、対するショウは余裕を崩す事無くこう言って、哂う。長く伸ばして黒い紐で括った紅い髪の一端を摘んで弄ぶ姿は、今のこの状況を愉しんでいる、と端的に物語るようでもあった。
「逐一気色悪ぃんだよ、てめぇは……! っと、とにかく、てめぇと遊んでるヒマは、オレにゃねぇんだ。
……『司』としての務め、正しく果たすのが、先なんでな」
甘さと艶を帯びた声に露骨に顔を顰めながらこう言うと、シオンは無空間へ手を翳し、そこに現れた太刀をしっかりと握って抜き放つ。夜気を裂く白刃の煌めきと低い声の告げた内容に、ショウは形の良い眉を寄せた。
「『司』としての務め……つまり、我の『餌』を減らすという事か。
……悪い子だな」
「黙れ、悪食雑食ど変態。『護界』の理乱すてめぇのやり方は、認めるわけにゃあいかねぇんだよ」
「本当に……お前は聞き分けのない子だな、『水牙』。もっとも……」
大げさな仕種でため息をついた後、ショウは摘んでいた髪を離して後ろへ追いやった。表情が僅かに険しさを帯び、その周囲にふわり、と紅い光が舞い散る。光は淡く揺らめく焔へと転じ、静かに渦を巻いた。
「もっとも……なんだよ?」
対するシオンは先に右腕に宿した氷霧を自身の周囲に巡らせつつ途切れた言葉の先を促し──直後に、それを後悔した。
「もっとも……そんな所もまた、我にとっては愛しくて仕方がないのだがな」
さらりと言いきるショウの口元には、愉しげな笑み。シオンに向けられる紅の瞳にはどこか狂的なものを感じさせる熱が込められている。
「いい加減にしろ……って、言ってんだろうがっ!」
その熱に嫌悪と苛立ちだけを返しつつ、シオンは手にした太刀を横薙ぎに振るう。刃が駆けた後の空間に三日月形の氷の刃が生じ、それは真っ直ぐ、ショウへ向けて飛んだ。
対するショウはす、と右の手を胸の前へと上げ、左から右へ軽く払うように動かす。それに応じるようにショウの周囲を渦巻く焔から火球が二つ飛び立ち、互いに絡み合う螺旋を描きながら氷の刃へと向かう。
氷と焔、対照的な二つの力がぶつかり──大気が、揺れた。
……リン……リリン……
ある所で血が流れ、ある所で力同士がぶつかる中。その中心に在る桜の大樹の周囲には、鈴の音が響いていた。
「…………」
我先に、と公園から逃れようとする人々の流れから離れたユウは、その音色に聴き入るようにじっと立ち尽くしていた。どこかぼんやりとした瞳は、今は薄紅をまとって揺れる桜の枝に引き付けられている。
「……きれいだなあ……」
零れ落ちた呟きは、周囲の喧騒の中では酷く場違いな響きを宿していた。そう遠くない所でヒトが異形に変じ、ヒトを襲って喰らっている、という状況下にも関わらず、ユウの意識はそちらには向かわない。少年の意識は季節外れの桜の美しさにのみ、向けられていた。
「……あれ?」
不意に、大きな瞳が瞬く。薄紅揺れる桜の枝、そこに人影が見えた気がしたのだ。ユウは首を傾げると、今見えたものを確かめるために桜の方へと歩き出す。が、一歩踏み出したところで、誰かがその腕を掴んで引きとめた。
「ユウくん? キミ、ミサの弟のユウくんでしょ!?」
上擦った声で名を呼ばれ、ユウは気だるげに振り返る。腕を掴んでいたのは、自分より二つか三つ年上の少女だった。見覚えのある顔にユウはほんの少し眉を寄せ、それから、何度か見かけている姉の友人である、と思い至った。
「何か、ご用ですか?」
ほんの少し首を傾げて問う姿はごく自然で日常的だった。とはいえ、異変が生じているこの状況においては、それは異常なものとして映る。ごく静かな調子で問い返された少女は、面食らったような表情でえ、と小さく声を上げた。
「何かご用、って……」
「何もないなら、離してください。ぼく、行きたい所があるんです」
戸惑う少女に淡々とこう言い放つと、ユウは掴まれた腕を振り払ってそちらに背を向ける。ゆっくりと桜の方へ向かう背を少女はしばし呆然と見送っていたが、やがて、待って、と言いつつユウへ向けて手を伸ばした。
「そっち、危ないから、一緒にひな……!」
一緒に避難を、という言葉を遮るように、何もなかった空間に砂塵が巻き起こった。突然の事に少女は足を止め、腕を翳して細かい砂粒から目を庇う。
「な……一体、なんなのよぉ……」
砂塵は一瞬で鎮まるものの、突然の出来事はそれ以上進む事をためらわせる。その間にユウの姿は見えなくなり、結局、少女は公園から急いで離れる方を選んで駆け出した。
リィン……リィィィ────ン……
幾度目か、鈴の音が響いて、宵の空に薄紅の花弁が舞う。
「いのちの、まつり。
こうさが、はじまる。
はじまるよ?」
その音色に重ねるように、稚いわらい声が響いて、消えた。